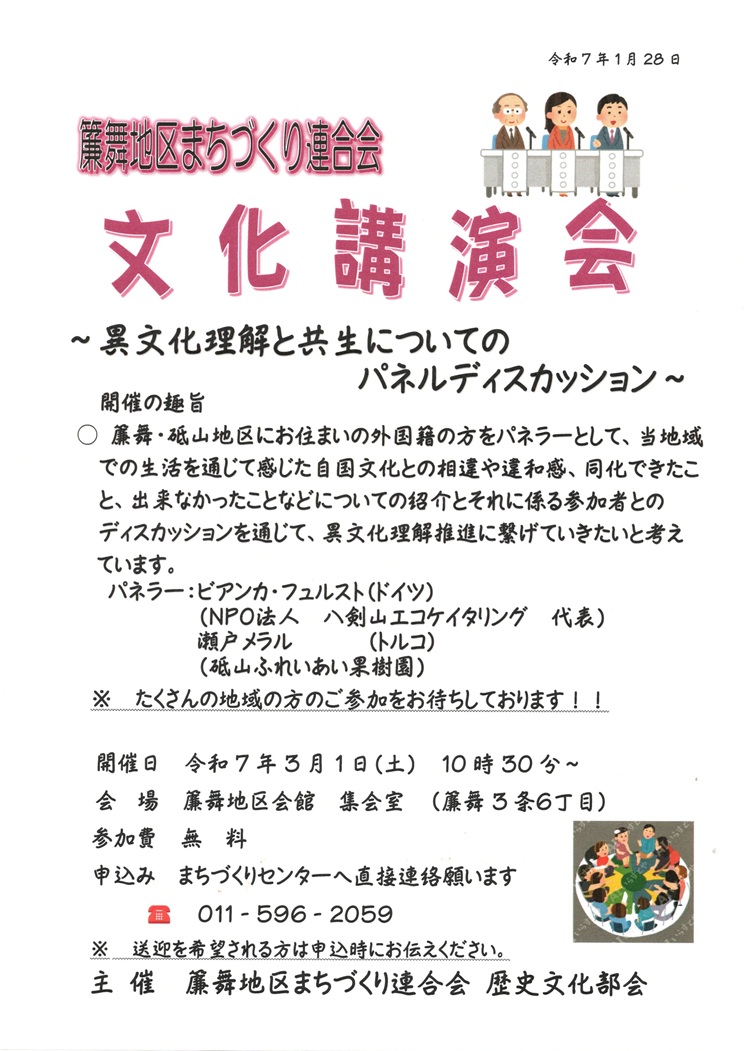「異文化理解」という言葉を耳にする機会が多くなっています。この「異文化理解」とはどういうことなのでしょうか?
私たちの周囲には「似て非なるもの」が結構沢山あるようです。
この「似て非なるもの」とは、「一見似ているようでいて、その内実はまったく違うこと」という意味です。
外観は同じように見えるが中身、すなわち性質や価値が本質的に全く異なっているという、「同じで異なる」もので、「文化」がその一番良い例かも知れません。
日本文化は、大昔からいろいろな「文化」の影響を受け、特に外来文化を非常に広く受け入れ、必要だと思うところは全部取り入れ、その「文化」が持っていた形を全部なし崩しにして自文化に同化させ、消化させて来たといわれます。それが「日本文化の重層的性格」だそうです。
外来文化の同化の例としては、外国の神様として導入した仏教、その後の仏教の日本化、唐文化の国風化、明治期の外来文化の導入等があり、料理としてもカレーライス、とんかつ、スパゲッティナポリタン等々があります。
ただし、外来文化を多く摂取してきたにもかかわらず、「異文化」に対して無理解の側面をもっているということも指摘されています。
現在、パレスチナ、ボスニア、北アイルランド、インドネシア他、世界各地で紛争が起こっていますが、宗教を始めとする「文化」の対立や衝突がこれらの一因でもあります。
グローバル化が進展している中、「異文化」に出会う機会が日常化しつつある現在こそ、「異文化理解」が重要な意味を持つことになるのではないでしょうか。
なぜならば、「異文化」への無知や無理解が偏見や差別の大きな原因となるからです。
「異文化理解」とは、互いの異を知り、それを認め合うことであり、それが「国際理解」への第1歩となると考えられます。
人々が築いてきた「文化」の多様性の価値を認め、「文化」の違いが人間存在にとって深い意味を持つことを理解することが大きな意味を持っており、「異文化理解」が「共生」へ向けてのキーワードであることも理解する必要があると思われます。
今回、簾舞・砥山地区に長らく住まわれてきた「外国人」をパネリストとして、当地域での生活を通して感じた自国文化との相違や違和感、そして同化出来たこと、出来なかったことなどについての紹介とそれに係る参加者とのディスカッションを通じて、「異文化理解」の推進を図りたいと考えています。
当日のパネリストは、
(1)ビアンカ・フュルストさん(NPO法人「八剣山エコケータリング」代表)
ドイツで生まれ育ち、ドイツの大学で日本学を学ぶ。その後、熊本大学に留学し、そして札幌国際プラザの国際交流員として来札。
札幌市の環境保全アドバイザーを務め、配偶者は「八剣山果樹園」の櫻井さん。
(2)瀨戸メラルさん(砥山ふれあい果樹園)
トルコで生まれ育ち、トルコの大学で観光ホテル関係を学び、地元ホテルに就職。瀬戸さんと知り合い、1998年に来日し結婚。
来日後、日本語学校で日本語を学び、ふれあい果樹園の業務に従事しながら、ジャイカからの国際農業研修団等の対応にも従事。農閑期には愛知県のトヨタ自動車工場でトルコ語通訳としても従事。
・日 時 3月 1日(土)10:30~
・場 所 簾舞地区会館 集会室
・無料
・LLP北海道による地域内での無料送迎あり(申込時に希望を伝えてください)。
・申込み 簾舞まちづくりセンター(596-2059)